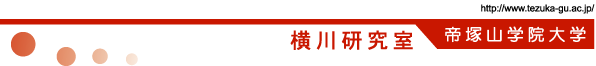 
私たちは、「小さい」「優しい」「おっとりしている」と生徒に言われる横川寿美子先生に指導して頂いています。趣味は、映画☆好きな本は、『若草物語』と言う先生。
そんな横川先生の児童文学を始めたきっかけは、大人の文学には救いがなく子どもの文学にはあると思ったから。児童文学を研究していて良かったと思うときは、色々な人と出会えて共通の話題があること。さらに、嫌だと思うときは、夢のある仕事ですねと言われた時…。これから児童文学を始めようと思う人に一言と質問すると「自分でも気づかなかった子どもの頃のことが整理でき、わかるかもしれません」と笑顔で答えて頂きました!! |
 |
| 横川寿美子先生を囲んで |
|
私たちのゼミの人数は9人で先生を合わせてとても仲がとても良い楽しいクラスです。今年の9月2・3日には、箱根の「星の王子様ミュージアム」へ行きました。新幹線では、先生の好きなマンガや今までお会いしたことのある児童文学者のお話などサラリーマンの多い金曜の新幹線の中でとても盛り上がりました。
普段の授業は、短い児童文学を読み、それについて1人が作者などを調べてきます。そして、物語について出た感想と疑問点について話し合います。今は、夏休みの間に読んだメアリー・ノートン著『床下の小人たち』のレポートを作成し、9人の意見を交換しています。「この物語によって何を伝えたいのか」など様々な意見の中でも説得力のある意見には感心させられます。
横川先生は、ゼミの途中で紅茶を入れてくれるのですが、最近ではケーキ屋でバイトしている子がいるのでちょっとしたお茶会になっています。美味しいものが食べられるのでゼミのある水曜日が早く来ないかと楽しみです!!
ゼミの仲間と仲良くなり、お互いに刺激しあいながら学ぶ児童文学の世界はとても勉強になります。さらに先生は、一人一人の意見を広げてくれます。そこが横川先生の魅力だと感じます。そして横川先生は、私たちの自慢の研究室の先生です。 |
|
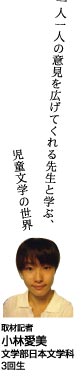
|
|
|