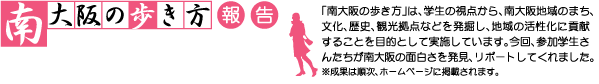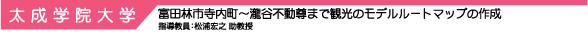
|
マップの作成を終えて
経営情報学部 久保田 健五

長いようであっという間の調査でした。僕たちが寺内町にフィールドワークに出かけたときは、まだ少し歩けば汗ばむような季節だったと思います。自分の大学のすぐ近くに寺内町という町があることも知らず、全くのあそび気分で、どちらかと言えば、嫌々気分で先生の後に付いて行ったことが、つい昨日の出来事のようです。でも何度も何度も現地に足を運ぶうちに、いつの間にか、木の葉が散り、そして雪が舞い、年末のせわしなさやお正月の飾り付けを横目にしながら、調査は続きました。 |

松浦教授お薦めたこ焼き

|
そのうち何度行っても新しい疑問が生まれ、確認をしたくなり現場にまた足を運びました。小さな壊れた石碑の歴史に思いを馳せ、朽ちはてた建物にかつての人々の生活を感じようとしました。地面に寝そべり、堀跡に頭をつっこみ時の流れを探そうとしました。最初は、町ですれ違う住人の方々に怪しまれているようで、その視線がとても気になりました。自分の居場所ではない違和感をみんな強烈に感じたものです。しかし年も明け、お正月が過ぎ、この調査の仕上げの時期になってくると、もうこの町に、自分の家があるような錯覚さえおぼえるようになってきたのです。
見知らぬ町が、身近な自分の町に感じたとき、そこには、愛着というかその町への愛情と誇りが芽生えてくることを知りました。そうなるともう、我々の調査は単なる調査ではなく、発表は単なる発表ではなくなりました。それは誇るべき我が子を自慢する「親ばか」気分とでもいうのでしょうか。難波パークスでの発表は、何とも不思議な、自信に満ちた発表になってしまいました。また、あの発表会に参加されていた、見知らぬ方から、私たちの作成した地図に従って、「寺内町〜瀧谷不動尊を歩きました。」と、いうお便りを頂きました。とてもうれしかったです。ありがとうございました。 |
 |
| 瀧谷不動尊の縁日 |
|
今、振り返ってみると、『あの時の自信はどこからきたのだろうか』と恥ずかしくなってきます。でも「21世紀の観光」ってなんだろうと考えると、生意気かもしれませんが、これまでのような単なる物見遊山的な表面的なものでなく、地元住民と行政とそしてビジネスが、調和することは勿論ながら、更に、その場所への愛情と敬意が、しっかり感じられる観光でなくてはならないような気がします。また観光をする側の人間の意識向上も必要でしょう。今回僕たちは、このような機会を与えていただいたことに感謝いたしております。地域を調査すること以上に、人の生活に人の心を垣間見て人間を勉強したような気がします。最後になりましたが、このような機会を与えて頂いた指導教員の松浦宏之先生に心から感謝いたします。また南大阪コンソーシアムの職員の方々の暖かい応援がとも励ましになりました。この場をお借りして、お礼申し上げます。ありがとうございました。
|

■調査メンバー紹介
松浦宏之助教授:指導教員
お髭がじょりじょり。怒れば恐怖。ダンディでちょっぴり○○○な頼れる先生、でも尊敬しています。本来アラスカ地域研究が専門。今回、我々とずーっと調査に同行してくださいました。
板倉宏安(5年生):総合監修
いつのまにか現れ、いつの間にかいない。だがしかし、いつの間にか全体をまとめてくれる。古老的存在。現在、やっと卒業?日本一の△△△を目指して修行中。 |
 |
倉田一樹(3年生):資料記録担当
シンガポールの血が混ざったハーフ。だが英語がしゃべれない。涙もろいのが玉にきず。現在、母国で貿易会社立ち上げるために、英語の猛勉強中。
工藤昌弘(3年生):写真撮影・作図担当
青森出身。絵を描くのが趣味。今回、写真撮影に目覚める。また大酒のみでもある。
現在、自転車で世界を旅し、写真と絵を描くという壮大な夢に向かって、英語の猛勉強中。
久保田健五(4年生):レポート作成担当
この春、無事卒業。思いこんだら一直線。まわりが見えなくなる。雨の日も台風の日も黙々と現地調査へと向かう彼を、誰も止められなかった。調査後の今なお、自分の作った地図を片手に、寺内町に出没し、ひとり更なる調査を継続しているという噂である。現在、レスキュー隊員をめざして猛勉強中。 |
|
|
|
|
|
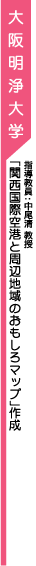 |
国登録有形文化財 山田家を訪ねて
観光学部 中村 文寛

今回、山田家に行ってとてもいい体験ができました。ゼミのみんなと何処かに泊まりに行くことが今までなかったので楽しみにしていました。
また、韓国の留学生も来ていて、仲良くなれたし一緒に夕食も食べ、いい思い出になりました。夕食は泉南市の地域の方々が作ってくれて本当に美味しかったです。特におでんが最高でした。ありがとうございました。
|
 |
| 国登録有形文化財山田家 |

|
夕食を食べた後に泉南市の地域のみなさんにゼミの活動について発表しました。このように地域のみなさんと大学の話しをするという機会は普段あまりないと思うのでよかったです。夜はみんなでお酒を飲み、いっぱい話しをして打ち解けられたと思います。日頃、そんなに韓国の人達と話すことがないのでとても新鮮でした。
屋敷地には主屋のほか、米蔵、土蔵、表門、長屋門などがあり、さすが国登録有形文化財だなと思いました。めったにこのような所に泊まることは出来ないので本当に貴重な体験をさせていただきました。山田家の奥さんにも大変お世話になりありがとうございました。
次の日は、天気が少し悪かったけど朝からみんなでフィールドワークをしました。山田家から和泉砂川駅までというルートで熊野街道を通って行きたくさんの文化財が現在も残されていました。厩戸王子跡、海会寺跡、本陣などがあり熊野街道の歴史を知ることができ勉強になりました。街道には、自然も残っており空気も景色も良く歩いていて気持ち良かったです。
途中、信達宿に寄り中を見学させていただきました。昔、紀州藩主も参勤交代の往復で宿泊していたほど街道交通の要地だったとご主人はおっしゃっていました。それだけ、当時は重要な建物だったんだなと思いました。そのようなところに入らせてもらい本当に良かったです。信達宿の方には傘を貸してもらい助かりました。 |
|
|
山田家住宅、熊野街道に行って思ったことは、泉南市にはたくさんの歴史を学ぶところがあるところだということです。もっとこのような資源を残し大事にしていかなくてはならないと思います。こんなにも素晴らしいものがたくさんあるので泉南の観光はもっともっと盛んになっていくと思います。
この二日間で、本当にいい経験ができいい思い出になりました。韓国の留学生とも仲良くなれたし、色々な面で学ぶことの多い二日間でした。またこのような体験する機会があれば是非参加したいと思います。
|
|
|

関空会社を訪ねて
観光学部 八倉 昌明

関西空港は、米国同時多発テロや新型肺炎(SARS)などで国際線の便数が減少したが、今は順調に回復に向かっている。中国線は成田空港発着便を抜いて日本一と中国線が充実している空港となっている。
問題は国内線である。東京線を意識しすぎてか、新幹線と過剰に対抗しようとしすぎている。そのため、主要都市線が伊丹空港発着へとシフトした。関西空港のターミナルは画期的なもので、国内線・国際線の乗り継ぎが同一ターミナルで可能である。このターミナルをフルに活かせば、成田空港に勝つことができると私は確信している。日本各地から関西空港に集まり、国際線に乗り継いで海外に行く。こうすれば利用者のニーズや利便性を無視し、二極化している東京の空港に勝つことができる。 韓国・仁川空港、シンガポール・チャンギ空港など、超大型空港が相次いで開港している。関西空港の生き残りをかけ、私はトランジットツアーの将来性を期待している。日本は物価が高く、国土も狭いので大型空港の建設が難しい。必要経費も高価になってしまう。トランジットツアーでは、逆の発想で、高価なイメージを割り切ることから始める。日本にしかない物を、通過旅客に体験・見学・購入してもらうのである。温泉観光や寺院見学、日本製の電化製品・薬品など世界に誇れる物品を市販価格で提供する事で、あえて「日本経由で第三国に行こう」と思ってくれる空港にすることにある。ホテルやレストランなどを新規に造らなくてもよい。今、点としてある観光施設などを、わかりやすく線で結ぶだけでよい。これは、空港周辺の活性化にも繋がる簡単で画期的なものと考えている次第である。
|
|
まち歩きを終えて
国際コミュニケーション学部国際観光学科前田ゼミ 原田 言美

私たち、阪南大学前田ゼミでは、「堺市における魅力発見のまち歩き」として、3班に分かれて調査しました。1班は12月2日に、堺市博物館・自転車博物館・おかよし味匠庵さん・てくてくろーどについて、2班は12月4日に、堺市博物館・自転車博物館・河井慶長・てくてくろーどについて、そして、3班は12月6日に、南宗寺・藤井刃物製作所・てくてくろーどについて、それぞれ調査しました。
|
 |
| 包丁の加工体験に挑戦! |
|
この調査の目的は、「観光まちづくり」の可能性、「まち歩き」による「出会い体験」、暮らしの中の魅力発見、観光と生活のあらたな関係の可能性を検討する…などです。実際に、和菓子作りや刃物作りを体験してみて、普段では入ることのできない作業場で、プロが使っている道具・材料をそのまま使わせていただいて、すごく貴重な体験をさせていただいたと思います。私は、包丁を作らせていただきましたが、初めは作れるかどうか不安でした。でも、やさしく教えてくださり、とても楽しく作ることが出来たし、自分の作った包丁(自分の名前入り)はすごく愛着が持て、包丁に対する考え方も変わってきます。
今回の調査のまとめとして、私たちは3つのポイントを考えました。
1)堺の宝は「人」そのものであり、そして、その人の「暮らし」である。
2)堺の観光魅力は、伝統産業・伝統文化・この2つが今に生きている暮らしの三位一体型である。
3)堺では「暮らしの魅力」発見型観光が創出できるのではないだろうか…
というものです。
今回、このような調査をすることが出来たのは、住民の人たちが観光まちづくりの主旨を理解してくださり、積極的に協力していただいたからです。今後も、私たち学生と住民の人たちが連携して、新たなまちづくりが進むことを願っています。
|
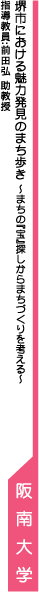
|
 |
 |
| おかよし味匠庵さん前で |
堺の自転車博物館 |
|
|