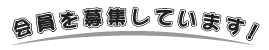
|
南大阪地域大学コンソーシアムの会員になりませんか?当コンソーシアムは、南大阪地域の大学や大学関係者の皆さまの参画により運営されています。大学相互の連携や地域社会の発展に向けた事業に参画・協力ください。
会員区分:団体会員(年会費20万円~50万円)
個人会員(年会費1万円) |

|
世界に開かれたゲートウェイ
人に、環境にやさしく
関西国際空港 |

|
関西国際空港(株)は南大阪地域大学コンソーシアムの運営を支援しています。 |
|
|
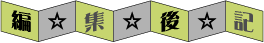
|
|
☆穏やかな春なのに世界情勢は混迷。私達コンソーシアムも、異文化理解と世界平和を視野に入れて、小さな活動を積み重ねていきたいと思います。(あ)☆大コンも2年目に入り、さぁこれからだ!という時に人事異動。関係者の皆さん大変お世話になりましたm(__)mこれからも“南”大コンを応援しています!(う)☆怒涛の半年が終わり、ほっ。桜前線とともにコンソも花開きますように。(ん) |
特定非営利活動法人南大阪地域大学コンソーシアム
ニュースレター第1号(2003年5月1日発行)
発行:特定非営利活動法人 南大阪地域大学コンソーシアム事務局
〒591-8025 堺市長曽根町130-23 堺商工会議所会館5F
TEL&FAX (072)201-6868
Eメール office@osaka-unicon.org
ホームページ http://www.osaka-unicon.org |
|
|